第六話 牙城クスコ(7)
一方、翌日、トゥパク・アマルからの呼び出しの知らせを部下から受けたフランシスコは、すっかりやつれた顔面をいっそう蒼白にした。
ただでさえ細面のその輪郭は今や頬がこけ、目はすっかり窪み、その下には黒ずんだ隈ができている。
(トゥパク・アマル様は、きっと、昨日の戦場でのわたしの醜態をディエゴから聞いたに相違ない…――!!)
にわかに呼吸が息苦しくなり、油汗が幾筋も彼の横顔を伝う。
己の天幕の中で、フランシスコは頭を両手で抱え、思わずその場にうずくまった。
今すぐ、この場から消えてなくなりたい、それほどのひどく切迫した思いに駆られながらも、しかし、トゥパク・アマルに呼び出されているのに出向かぬわけにはいかなかった。
彼は力無く立ち上がると、激しい眩暈をこらえながら、ふらつく足取りでトゥパク・アマルの天幕に向かう。

トゥパク・アマルの天幕の前では、いつものようにビルカパサが警護の目を光らせていたが、そちらに向かっていくフランシスコの姿を見ると笑顔を向けてきた。
しかし、フランシスコの何やらただならぬ様子に、ビルカパサは「フランシスコ殿、酷くお辛そうですが、まだ具合がお悪いのですか?」と、心配そうに聞いてくる。
「いや、どうということはないのだ」と擦れた声で答えながらも、フランシスコにはビルカパサの態度がひどく白々しいものに思える。
常にトゥパク・アマル様の傍近くにいるこの男のこと、もはや全て知っているに相違あるまいに、このわたしのことを情けないと腹の内では酷く呆れていることであろう。
一方、当然ながら何も聞かされていないビルカパサには、そんなフランシスコの内面の声など想像だにつかぬまま、「トゥパク・アマル様、フランシスコ殿がお見えです」と、天幕の中に声をかける。
「入ってもらっておくれ。それから、ビルカパサ、そなたは暫くはずしていておくれ」と、天幕の内側からトゥパク・アマルの声がする。
「畏(かしこ)まりました」と恭しく返事をすると、ビルカパサは丁寧な手つきで天幕の布を掲げ、「さあ、フランシスコ殿、どうぞ中へ」と、いつもと変わらぬ笑顔で促した。
フランシスコがおずおずと天幕の中へ入ると、トゥパク・アマルは寝台の上に身を起こして腰掛け、何やら自分で腕の包帯を巻き直しているようだった。
自由に動く右手だけを使って、左腕の傷口に何とか巻きつけようとしているようだが、器用なトゥパク・アマルには珍しく、なかなか苦戦している様子である。
そして、すぐにフランシスコの方に視線を向けて、「やはり医師のようには、うまく巻けないものだね。いや、一晩たったら、何だかほどけてきてしまってね」と、軽く肩を竦めて笑顔をつくった。
「お手伝いいたしましょう」と、思わずフランシスコは急ぎ足でトゥパク・アマルの傍に近づくと、身を屈めて包帯を受け取り、丁寧に巻きはじめた。
「ありがとう」と、トゥパク・アマルもフランシスコに任せ、穏やかな眼差しで、包帯を巻く相手の手つきを見守る。
「何やら、懐かしい気分になる」と、トゥパク・アマルが、ふと呟いた。
え?…――という眼差しで、フランシスコが顔を上げると、トゥパク・アマルは少し遠くを見るような目で、「昔、そなたとわたしが、まだクスコの神学校にいた頃、よく、そなたがこうして包帯を巻いてくれたではないか」と言う。
「ああ」と、包帯をほぼ巻き終えながら、フランシスコも思わず懐かしそうな声になる。
「そうでしたね。
あの頃のトゥパク・アマル様は、なかなかのワンパク者でしたからね。
よくお怪我をされていた」
「あの頃から、そなたは、まるでわたしの親代わりのように、よく面倒をみてくれていた」
トゥパク・アマルの深く穏やかな声に、思わず、フランシスコはトゥパク・アマルの方に向き直る。
トゥパク・アマルは目を細めながら、じっとフランシスコを見つめ、静かに微笑んでいた。
その眼差しに吸い込まれるように、フランシスコもトゥパク・アマルを見つめる。
「ずっとそなたがわたしを見守ってきてくれたように、今度は、わたしがそなたを守りたい。
だから、わたしの言うことをきいてほしい」
トゥパク・アマルの声は、あくまで静かで、深く、澄んでいる。
しかし、フランシスコは不意に、現実に引き戻される。
あの戦場での己の醜態に関することを、今、トゥパク・アマルは何か言おうとしているのだ、そう直観すると、背筋にゾクリと悪寒が走った。
短い沈黙の後、思いきったように、トゥパク・アマルが口を開く。
「そなたは、暫く、戦場に出てはならぬ」
トゥパク・アマルの声は、非常に穏やかであったが、しかし、ひどくきっぱりもしていた。
既に青白いフランシスコの顔面が、サッと血の気を失い蒼白になっていく。
その目には、悲痛な色が激しく浮かび上がった。
そのようなフランシスコの表情を見るトゥパク・アマルもまた、非常に苦しげになる。
トゥパク・アマルは、己のがっしりとした右腕をフランシスコの方に真っ直ぐ伸ばし、そのしなやかな褐色の指で相手の肩をしっかりと掴んだ。
そして、真正面から、フランシスコの目を真剣な眼差しで見据えた。
「今のそなたの心理状態で戦場に出るのは、自ら死にに行くようなものだ。
フランシスコ殿、どうか誤解をなされるな。
わたしは、そなたの心が、あのような戦場を耐え難いと感じていることを、決して責めているのでも、咎(とが)めているのでもない。
あれほどに残虐で血生臭い戦場を耐え難いと感じるそなたの感性は、全く恥じるものではない。
むしろ、それは、人として、備えていて然(しか)るべき美徳とも言える感性であろう。
だが、時と場面によって、求められる感性は異なってくる。
あのような戦場では、人の血や肉を見ても、何も感ぜぬほどの者の方が、結局は、よく動け、生き延びる。
どちらが良い、悪いではないのだ。
人は、それぞれ、己を偽らずにいられる場面でこそ、その力を存分に振るうことができるものだ。
それは、戦乱の今の世とて、変わりはせぬ。
今の状況とて、実際、戦場以外でも為すべき仕事は山ほどあるのだから。
フランシスコ殿、賢いそなたなら、わたしの話をわかってくれるね?」
あくまで静かに、一言一言を丁寧に話していくトゥパク・アマルの言葉を、しかし、フランシスコの遮断された心は、果たしてどれほど聴き取れていたことだろうか。
呆然と宙を見据えるフランシスコに、トゥパク・アマルは、精一杯の誠意をこめて、再び言う。
「わたしは、そなたを失いたくないのだ。
わかってくれるね」
それは、トゥパク・アマルの紛れもない真実の言葉であった。
しかしながら、もはや極度の自己卑下と疑心暗鬼に取り憑かれたフランシスコに、トゥパク・アマルの真心が果たしてどこまで伝わっただろう。
この役立たずの自分は、ついに、トゥパク・アマル様にも見放されたのだ…――!!

フランシスコは自分の足元が音を立てて崩れ落ちていくようなひどい感覚に襲われながら、一言も発することのできぬままトゥパク・アマルに一礼すると、柳のように頭を垂れて踵を返した。
フランシスコのうな垂れように強い懸念に憑かれたトゥパク・アマルは、思わず寝台から立ち上がる。
しかし、その瞬間、まるで高圧電流が流れたがごとくに、術後の傷跡に尋常ならざる激痛が走り、その場に崩れるように跪いた。
「フランシスコ殿…!」
苦しい息の中、去りゆく後姿に急ぎ呼びかけるが、もはやトゥパク・アマルの声も耳に入らぬほどに落胆したフランシスコは、そのまま消え入るように天幕を後にした。
一方、トゥパク・アマルの指示のもと、昨日からインカ軍の被害状況を調べていたアンドレスは、今、負傷兵たちの呻き声と血生臭い空気の充満する治療場を訪れていた。
治療場と言っても、本営の一隅の露天の空き地、及び、幾つかの専用の天幕が張られただけの極めてシンプルな場所である。
ただし、一見簡素なこの治療場ではあったが、そこに投入される食料や医薬品などの物資の手厚かったことは、いかにもあの道義心に篤い総指揮官トゥパク・アマルの陣営らしいことであった。
さらに、トゥパク・アマルの思いをそのまま反映するかのごとくに、負傷兵たちに対して、多数の従軍医やインカ族の女性たちが真心こめたいたわりの言葉をかけ、健気なほどに熱心に看護に当たる姿がとても印象的であった。
従軍医から状況報告を受けた後、アンドレス自身も治療場を視察して回った。
今回のクスコ戦で敵の銃弾及び刃物や鈍器に倒れた兵たちの状態は、想像を絶する悲惨なものであった。
多くの者が致命傷を負っており、回復を待たずに息を引きとっていた。
一つの天幕には、特に、瀕死の重態の負傷兵たちが集められている。
その天幕の入り口の布をめくったアンドレスは、その悲惨な光景に、一瞬、はっきりと目をそむけたほどだった。
そこにいる者たちは多くが、砲撃によってその身体の一部を失い、あるいは、火傷等のためか殆ど全身を包帯で巻かれた状態であった。
それらの者たちが地に累々と横たわり、地面には血糊がベッタリとこびリつき、空気は血生臭ささと、そして、夏の熱気のせいもあるのであろう、傷口から発せられる、まるで何かが腐っていくがごとくの強烈な臭気とで、とても息のできる状態ではない。
苦悶の表情のまま、アンドレスは改めて、昨日の「リマの褐色兵」のことを思い起こす。
この治療場にいる多くの者たちが、同じインカ族の者たちから受けた攻撃によって死にゆこうとしているのだ…――そう考えると、彼の胸は激しい憤怒と悲しみと理不尽さとで張り裂けそうになった。
もはや彼は、それ以上その現場を直視することができず、その場を離れかけた。
その時、不意にその同じ天幕の奥の方で、必死の様相で負傷兵の看護に当たるコイユールの姿が目に飛び込んだ。
アンドレスの心臓が、瞬間、完全に止まる。
彼は、はじかれたように、物陰に身を隠した。
しかし、どうしても、コイユールの方に視線が向いてしまう。

コイユールは、先刻のアンドレスの心の内をそのまま映し出したかのような、激しい憤怒と悲しみと理不尽さとを滲ませた横顔で、ただひたすら黙々と働いていた。
しかも、その表情には、これまでとは何か違う、いっそうひどく思いつめたような悲痛な色が浮かんでいるように思われた。
アンドレスは、瞬間、時も、場所も、己の立場も、完全に忘れてその姿に見入った。
その手を上腕の方まで赤々と血に染めながら、彼にとっては、とても直視しがたいような負傷兵たちの惨憺たる傷口に、もはや何の躊躇(ためら)いも見せず、コイユールの手は触れ、清め、薬を塗り、手を当てて痛みを取り、そして、最後には優しい微笑みを送って力づけていく。
恐らく、もう命の長くはない兵たちばかりだった。
どんな思いで微笑みを送っているのだろう…――改めて、見つめるアンドレスの目の中で、彼女のその微笑みは、あまりに悲しく儚く見える。
アンドレスは、突然、胸が苦しくなって、急ぎ、その場を離れた。
そのまま逃げ去るように治療場を後にすると、しかし、どうにも気持ちがひどく急(せ)かされるような、何かひどく居た堪まれぬ思いに憑かれ、走るようにして、本営のはずれの人気の無い林の中に入った。
周囲に人の気配の無いことを素早く確認すると、深い息をつく。
しかし、どうにも胸が苦しくて、彼は自分の胸に思わずその手を当てる。
そして、改めて、深く溜息をついた。
(本当に、俺は、何をやっているのだろう…――)
何にとも、誰にとも、つかぬまま、ただ漠然とそんな思いが込み上げた。
そのまま傍の大木の幹にもたれかかると、全身から力が抜け落ちていくのが感じられる。
脱力したように、その身を大木にあずけたまま、アンドレスはぼんやりと上空を見上げた。
高地の短い夏を謳歌するように緑の葉を輝かせる梢たちの隙間から、正午前の澄んだ蒼い晴天がのぞいている。
何も知らぬ人がそんな彼の姿をみかけたら、それは、まるで、ふっと天から舞い降りてきて空に帰る道を忘れて途方に暮れている、褐色の若い天使のように見えたかもしれない。

一方、放心しきって空を見ている当のアンドレスの脳裏に浮かんでくるのは、今は、どうしてもコイユールのことばかりだった。
(そういえば、昨夜もトゥパク・アマル様の手術の前に見かけたっけ…)
彼は、思いに耽ったような目になる。
トゥパク・アマル様の手術は成功したようだった。
コイユールは、手術の手伝いのために呼ばれていたのだろう。
手術前に見かけた時、とても真剣な目をしていたっけ…。
上空を見上げたまま、しかし、そんなふうに思いを巡らせはじめたアンドレスの目には、もはや空の色は映ってはいなかった。
心の中に占められた思いだけに、今、彼の全神経が収束されていく。
それは、全く、この反乱とは無関係なことばかりだったのだが。
もはや止められぬ思いとなって、これまで無理矢理に抑え込んできたものが、まるで箍がはずれて溢れ出すかのごとくに彼を呑み込んでいく。
(コイユール…昨晩のトゥパク・アマル様の手術の手伝いって、どのようなことをしたのだろう…)
コイユールのことだから、きっと、あの自然療法をやったのに相違ない。
アンドレスの手が無意識のうちに、己の額を押さえこむ。
彼はそのまま、瞼をギュッと閉じた。
(それでは、トゥパク・アマル様の傷口のあたりに手を当てていたのだろうか。
トゥパク・アマル様の腕に、コイユールが触れていたということか…――!)
突然、アンドレスの心がズキンと痛んだ。
 え、何だ…?!――と、本人自身も、己の心の動きと反応にとまどい、困惑した念に憑かれた。
え、何だ…?!――と、本人自身も、己の心の動きと反応にとまどい、困惑した念に憑かれた。
治療の手伝いのためなのだから、相手の腕に触れるなんて、あまりにも当然のことではないか、と、アンドレスの理性は必死で己の心を説得しようとする。
(だけど…!!)
今度は足元の緑の草に目を落とした。
考えてみれば、コイユールと知り合ってもう10年以上も経つし、もともとは母上の治療を通じて知り合って、幼い頃からコイユールの施術のことをずっと見てきたのに…俺自身が、やってもらったことって、たったの一度も無かったのではないか?
「そうだよな…それって、どういうことなんだ」
思わず、一人、呟いた。
そのような己の様子に気付きさえせず、そして、客観的に見れば、今この切迫した戦乱の最中(さなか)に熟考するようなこととは到底思えぬ問題に心は占められ、しかし、もはやアンドレスのその思考は止めることができなくなっていた。
(母上はともかく、マルセラだって、村の人たちだって、今は多くの負傷兵の者たちも、それに、あのトゥパク・アマル様さえ、ついには…――それなのに、一番はじめからコイユールのことを知っている俺は、一度もコイユールに、あの指を触れてもらったことがないんだぞ…それって…!)
「はあっ…」と無意識に大きな溜息をついてから、彼はやはり木にもたれたまま、腕組みをした。
昨夜、トゥパク・アマル様と、どうだったのだろう…。
コイユールは昔から、トゥパク・アマル様のことをすごく慕っていたからな。
手術中、何時間も一緒にいたんだよな。
コイユールは、その間、その指をずっとトゥパク・アマル様に触れていたのだ…――!!
突如、アンドレスの心臓がギュッと締め付けられるように痛んだ。
彼は激しく頭を振った。
「ああっ!!
もう、俺はこんな時に、一体、何を考えているのだっ!!」
すべてを振り払うように、アンドレスは叫んだ。
「アンドレス、そなた、どうしたのだ?」
突然、前方から声がした。
飛び上がらぬばかりにギョッとして、アンドレスは石のように身を縮め、完全に硬直した。
そして、全く滑稽なほどに、恐る恐る声の方を見る。
アンドレスの視線の先には、ロレンソが唖然とした表情で立っていた。
「な、なんだ、ロレンソか…!」
アンドレスはまだ驚きの余韻を引き摺りながらも、しかし、相手が朋友のロレンソであったことに、かなりホッとして深く胸を撫で下ろした。
一方、ロレンソは訝し気な表情のまま「なんだとは、なんだ?アンドレス」と切り返しながら、じっとアンドレスの顔を探るように見る。
「それにてしも…、アンドレス、今の完全な隙だらけのそなたの様子こそ、一体、なんだ?
敵の伏兵でもいようものなら、あっさり一撃であの世いきだったぞ」
呆れたようにそう言って、「何を考えていた?」と、詰め寄るように問う。
「な、何もっ…!!」とムキになって否定するアンドレスの方に、さらに、じぃっと視線を投げながら、「そんなはずはあるまい」と、ロレンソは淡々とした声でいなす。
そして、少しまじめな顔になって、「話ぐらいは、わたしにも聞けるぞ」と言いながら、傍の大木の幹に、その逞しく鍛えられた青銅色の腕を添えた。

夏の高地を吹き渡る涼やかな風が、緑の梢を揺らしながら、さらさらと優しい音を立てていく。
まるで精霊が奏でゆくかのようなその心地よい音色に、二人は暫し聞き入った。
ロレンソは辺りに漂う爽やかな夏の草木の香りを全身に吸い込むような仕草をすると、「この景色の中にいると、戦乱の中にあるなんて嘘みたいに思えてくる」と、静かに言った。
アンドレスも頷く。
「本当に…」
そんなアンドレスの方を、ロレンソは真っ直ぐに見た。
「アンドレス、そなた、誰か想う人があるのであろう」
ロレンソのその真摯な眼差しは、決して冷やかしたものではなく、包み込むような誠意に溢れたものであった。
その瞳に吸い込まれるように、アンドレスは一瞬その首を縦に振りかけるが、ハッと我に返ると、「そっ…そんな人、いるわけがないだろう!!」と慌てて否定した。
己の口調に必要以上な力が入ってしまい、かえって決まり悪い思いに憑かれ、彼は反射的にロレンソから視線をそらす。
そして、もはや己の意思ではどうにも止められぬままに微かに頬を染め、足元の草地に目を落とした。
ロレンソの目の中で、もう長い付き合いになる友のその横顔は、己の言葉が真実ではないことをあまりにもありありと物語っている。
「わたしにまで隠すことはないのに」と、ロレンソの声は少しだけ寂しそうだった。
「そなたのような、溢れるほどに情感豊かな者が、誰も想う者がないなどありえぬことだ。
そんなことなら、むしろ、その方が不自然というものだ」
揺れる眼差しで再び顔を上げたアンドレスに、ロレンソは目を細めて頷いた。
「ロレンソ…」と呟くアンドレスの瞳の中で、ロレンソは、いつも通りの、あの大人びた表情のままに微笑んでいる。
「アンドレス、わたしたちは、どのような立場や境遇にあろうとも、本質は誰もが同じ一人の人間。
そうだろう?
もちろん、そのようなこと、今更、そなたのように、昔から誰にでも分け隔て無き者に言うまでもないことだが…。
なあ、アンドレス…この戦(いくさ)で、そなたがどれほどトゥパク・アマル様からのご期待を受けているか、そなたがインカ軍で果たすべき役割がどれほどに重責を伴うことか、わたしなりに良くわかっているつもりだ。
だが、だからと言って、誰かを愛してはいけない、などということはあるまい。
どのような状況にあろうとも、そなたは、変わらず、そなた、なのだ。
意識の上で己の感情を殺そうとすれば、逆に、無意識の中でそれに縛られる。
己の感情を殺すことと、己の感情を統制することとは、違うのだから…。
アンドレス、そなたの全てをそなた自身が受け入れ、真(まこと)のそなた自身であってこそ、真の意味で他者の全てをも受け入れられる…――それは、将として必要な器でもあると思うのだが…」
そう言って、ロレンソは、包み込むような眼差しでアンドレスの瞳を見つめた。
一方、ロレンソの言葉に、アンドレスは息を呑んだ。
コイユールのことなど知る由もないこの眼前の友は、しかし、まるで全てを見抜いているかのごとくに、己の心が迷い求める答えを与えようとしているかのようにさえ思われた。

アンドレスは胸の中に熱いものが激しく込み上げるのを感じながら、はじめて素直に、本当に、この世界で全くはじめて、自分の想いを自分以外の者の前に明らかにする。
「とても大事に想う女性(ひと)がいる」
はじめて自分の声となって外側からその言葉を聞き、アンドレス自身が驚いたように目を見開いた。
その胸の鼓動が、にわかに速くなる。
「そうか」と、ロレンソは変わらぬ包み込む眼差しで、胸の内を明かしてくれた友の方を真っ直ぐに見つめた。
そして、「その女性(ひと)とは、いかなるお方なのか?」と、穏やかな声で問う。
アンドレスの揺れる瞳が、ふっと遠くなる。
暫し、沈黙が流れた。
次第に高くなる夏の太陽が、二人の若者の褐色の皮膚に、熱を帯びた陽光を降り注ぎはじめた。
アンドレスがこれ以上は口を開きそうにないのを察したロレンソは、変わらぬ穏やかな口調で問いかける。
「マルセラ殿か?」
え?…――という表情でロレンソに視線を返したアンドレスの目に、ロレンソは静かに微笑み返す。
「違うかとは思ったけれど、念のため、聞いておきたかったのだ」
ロレンソの意味ありげな言葉に、今度はアンドレスが身を乗り出した。
「もしかして、ロレンソ…!
マルセラを?!」
思わず目を瞬きながら夢中で自分の顔を覗き込んでいるアンドレスに、ロレンソは落ち着いた声で応ずる。
「ああ、そうだ。
そなたとは恋敵にはなりたくなくてね」
「そうだったのか…!!」
アンドレスは深い感慨を込めた声で言う。
そして、瞳を輝かせながら、大切な朋友を眩しそうに見つめた。
「マルセラは、昔から男勝りで、闊達で、まるで少年のようだった。
でも、本当はとても心根の美しい、気立ての優しい女性だと思う。
そうか、マルセラを…君が…!!」
感動を素直に滲ませながら、あの輝くような笑顔でロレンソを見つめるアンドレスを、ロレンソは涼やかな大人びた眼差しで、「そなたにそう言ってもらえるのは嬉しい」と応える。
しかし、少し低い声でつけ加えた。
「だが、マルセラ殿が本当に想っているのは、そなたのことだぞ。
アンドレス」
「え?!」
アンドレスは目を見開き、固唾を呑む。
ロレンソは目を細め、僅かに、視線をそらした。
「まさか…。マルセラが、お…俺を…?」と、やや混乱した目の色で呟くアンドレスに、ロレンソは微かに溜息をつく。
「そなたは、こうしたことには、全く鈍感なのだな」
そして、少し寂しそうに微笑んだ。
アンドレスは返す言葉が無く、ひどく戸惑った表情のまま、眼前の友の顔を見ては、また慌てて足元に視線を落とし、そんなことを交互に繰り返している。
そんなアンドレスの肩に手を置いて、ロレンソはいつもの大人びた笑顔を真正面から向けた。
「これはわたしと、そして、マルセラ殿との問題だ。気にするな。それより…」と、改めてアンドレスの瞳のずっと奥の方まで深く見据える。
「そなた自身の想いを形にせねばなるまい。
己の心を偽ってはならぬ。
真の心の声は、真にあるべき方向を指し示しているのだから」
アンドレスは言葉も無く、しかし、強く胸に迫りくるものを感じながら、吸い込まれるようにロレンソの目を見つめた。
己の心の中で非常に固く凍っていた何物かが、光を浴びて、僅かながらも氷解しはじめた…――そんな感覚であった。

さて、再び、物語を現実的な状況に戻そう。
あのクスコ戦以来、トゥパク・アマル率いる反乱軍とクスコのスペイン軍とは、互いにピチュ山を隔て、無言の睨み合いを続けたまま数日間が過ぎていた。
そのような状況の中、全身から激昂のオーラを発し、まるで鬼のごとくの形相をした一人のインカ族の男が狂ったような勢いで馬を駆り、トゥパク・アマルの本営に乗り込んできた。
本営入り口の兵たちが必死で止めるにもかかわらず、男は乗馬のまま砂塵を蹴散らし、トゥパク・アマルの天幕まで、まるで切り込むがごとくの勢いで馬を乗り入れた。
「何事だ?!」
衛兵たちが血相を変える中、すぐにビルカパサが騒然としている兵たちをかきわけ、衆目の中央にいるその人物の方に飛び出していった。
その人物はビルカパサの方を見るなり、「トゥパク・アマルはどこだ?!」と、真っ黒な埃にまみれた顔で怒鳴るように言い放つ。
「アパサ殿…!!」
ビルカパサは、予想だにしない突然の来訪者に、思わず目を疑った。
トゥパク・アマルの有力な同盟者の一人であるこのアパサは、反乱幕開けと共に、このペルー副王領に隣接するラ・プラタ副王領にて挙兵してから、実に多くの戦果を上げていた。
しかしながら、現在も、アパサはラ・プラタ副王領で兵を指揮しているはずだった。
目を見開いているビルカパサに、アパサは、チッと地面に唾を吐いた。
「あのクスコでの、トゥパク・アマルの目も当てられぬ惨敗を聞いて、こうしてわざわざ素っ飛んできたのだ。
なに、心配するな。
本拠地の方は、できる部下に任せてある」
しごく簡単に説明した後、「それより、トゥパク・アマルに会わせろ!!あの、とんでも野郎に!!」と、目を吊り上げてビルカパサに詰め寄った。
ビルカパサは、改めて、アパサを見た。
実際、アパサは全身、土と埃と汗まみれで、何日間も一目散に馬を飛ばし続けてきたことは一目瞭然だった。
まともに食事もとっていないのではないかと思われるほど頬骨も出ていたが、眼だけは不気味なほどに炯炯として鬼気とした迫力が漲っている。
ビルカパサは、「アパサ殿、本当に、よくお越しくだされた。トゥパク・アマル様も、さぞ驚かれるであろう」と言ってから、「いや、お喜びになられるであろう」と慌てて言い直す。
そんなビルカパサに冷ややかな視線を投げて、「何だ?俺は招かれざる客か?!」と憎々しげにアパサが言う。
ビルカパサは「まさか」と手で軽くいなし、「まあ、どうかお気を悪くせずに。アパサ殿のお働きにはトゥパク・アマル様はもちろん、我々側近一同も、深く敬意を抱いているのですから」と、なだめるように言いながらトゥパク・アマルの天幕の方にいざなっていく。
そんなやり取りをしながらこちらに向かってくる二人を見つけたアンドレスは、彼もまた、一瞬、目を疑ったように頭を振った。
そして、改めて、喰い入るように前方を見据える。
「アパサ殿!!
やはり、アパサ殿!!」
アンドレスは半ば叫ぶように言うと、感極まった表情で、そちらに走り込んでいく。
「アパサ殿!!
本当に、アパサ殿ではないですか」
歓喜の声で己の名を幾度も呼ぶ眼前の若者を見るアパサの目も、思わず懐かしさと不意に込み上げる特別な思い入れから、その光を和らげる。
国中探しても右に出る者のそうはない程に武勇に秀でたこのアパサは、トゥパク・アマルに見込まれて、かつてアンドレスに武術を一から叩き込んだ師でもあったのだ。
「アンドレス」
「アパサ殿!!」
二人は、互いの目を真っ直ぐに見つめ合い、あまりに深い感慨故に言葉にならぬ思いを無言で交し合う。
それから、どちらからともなく、がっしりとその腕で抱擁した。
ビルカパサも、そんな二人を、思わず目を細めて眩しそうに見守る。
「それにしても、どうされたのです、アパサ殿。
突然、このようなところまでお見えになるとは。
アパサ殿は、ラ・プラタ副王領にて、今も軍を指揮している真っ最中かと思っていましたが…」
そんなアンドレスに、アパサは再び険しい表情になって、苛々と貧乏ゆすりのように体を揺らした。
「トゥパク・アマルに話があってきた。
…ったく、あの野郎、いい加減にしやがれよ」
殆ど独り言のように、しかも、吐き捨てるように言う。
ビルカパサは既にアパサの言わんことを察して、難しい表情になっている。
しかしながら、恐らく何日も馬を飛ばしてここまで馳せ参じたアパサを、まさか無碍(むげ)に追い返すわけにもいかなかった。
「トゥパク・アマル様に取り次いで参ります。
暫し、お待ちを」
そう言い残し、ビルカパサはトゥパク・アマルの天幕に向かった。
彼が天幕に入ると、まだ負傷の後遺症を引き摺りながらも最近では大分自由に動けるようになってきたトゥパク・アマルが、既に外の騒然とした気配を察して、「何事か?」と静かに問うてくる。
「はい。
アパサ殿が、トゥパク・アマル様とのお目通りをと、ご来訪でございます」
ビルカパサが恭しくも、少々案ずる眼差しでトゥパク・アマルを見た。
「アパサ殿が…!」と、トゥパク・アマルも少なからず驚きの色を見せるが、「すぐに通してくれ」と、真摯な声で言う。
「はっ!」
再び、恭しく礼をして、ビルカパサは急ぎアパサを呼びにいく。
間もなく、アパサがドカドカと足音荒く、トゥパク・アマルの天幕に乗り込むがごとくに現われた。
トゥパク・アマルは、思わず懐かしさの感情が先に立つ。
「アパサ殿!!
よくお越しくだされた」
そんなトゥパク・アマルの様子を完全に無視して、アパサはズカズカとトゥパク・アマルの鼻先まで迫り来ると、「おまえ!!何を考えている!!」と獰猛に睨みつけた。
そして、トゥパク・アマルが立ち上がる間も与えず、その口角から唾を飛び散らせながら、猛り狂った鬼のような剣幕で捲(ま)くし立てはじめる。
「トゥパク・アマル!!
おまえ、クスコ戦のあの時、何故、リマの褐色兵どもを討たなかった!!
たとえインカ族であろうとも、敵は敵だ!!
あの時…、あの時、おまえが怯(ひる)みさえしなければ…今頃、クスコは必ず奪還できていた!
さすれば、この国の、この最悪の植民地支配を瓦解せしめられていたに相違ないのだ!!
それを、おまえは…!!」
両目をこれ以上ないほど吊り上げて荒れ狂うアパサは、しかし、最後は、あまりの無念さからであろう、思わず言葉に詰まり声にならぬほどであった。

トゥパク・アマルも、そして、周囲に集まってきていた側近の者たちも、思わず、すぐには返す言葉が出ない。
恐らく、皆、心のどこかでは、同じ思いがあったのかもしれなかった。
「トゥパク・アマル…、おまえの、その判断の誤りが…結局は、あの褐色の敵兵たちの何十倍、何百倍ものインカ族の兵を、そして、民衆を、再び苦境に追い込むことになっていくのだ…!!」
憤怒と悔しさのために震える声でそう言うと、もはや、感情を押さえきれぬアパサは、トゥパク・アマルの胸倉に掴みかかった。
「いいかっ!!
これ以上、こんな馬鹿げたことは、やめるのだ!!
すぐに、あのリマから来た褐色兵どもを一掃しろ!!
トゥパク・アマル!!」
無抵抗のままに胸倉を掴まれ、揺さぶられ、アパサの為すがままになっているトゥパク・アマルを見かねたディエゴとビルカパサが、ついに溜まりかねて背後からアパサを押さえ込む。
「アパサ殿、いい加減に…!」と、険しい声で制しかけるディエゴに、トゥパク・アマルは沈着な、だが、毅然とした声で、「アパサ殿をお放しするのだ」と言う。
アパサは背後の二人を「チッ!」と鋭く不遜な視線で一瞥し、押さえ込まれていた腕を荒々しく引き抜いた。
それから、アパサは、改めて、トゥパク・アマルに、にじり寄った。
そして、今度は、地底から湧きだすような、感情を押し殺した低い声になって、まるで勧告を突きつけるがごとくに言う。
「わかったな…?
すぐに、奴らを討ち倒すのだ。
おまえが本当にインカのことを思うなら、今こそ、それを示せ…――トゥパク・アマル!!」
貫くように己を険しく見据えるアパサの眼は、トゥパク・アマルがこれまで知るうちで、この男の最も真剣なものだった。
「アパサ殿…」
トゥパク・アマルは苦しげな、しかしながら、ゆるぎなき眼差しで、真正面から相手の目の奥を見返した。
「それはできぬ。
同じインカ族を殺すことはできぬ」
「おまえ…まだ、そんなことを…!!」
瞬間、アパサの髪がメラメラと逆立った。
「アパサ殿、ここはわたしに任せてほしい。
考えがあるのだ」
「何だ!!
言ってみろ」
もはや怒りの極みに達し、目を白黒させながらアパサが吐き捨てるように言い放つ。
「褐色兵の将と話し合い、説得する」
トゥパク・アマルの声は、さざ波ひとつない湖面のように静かである。
アパサの目元がぴくぴくと引きつるように痙攣しはじめた。
もはや、言葉も無い、と言わんばかりの形相である。
長い沈黙の後、アパサは言った。
「…――トゥパク・アマル。
おまえとは、もはやこれまでだ」
ぶち切れるのをギリギリ押さえているかのような、氷のごとくに冷ややかな声であった。
「アパサ殿…」
トゥパク・アマルも眉間に皺を寄せる。
「アパサ殿、インカ族同志で血を流し合うなど、いかなる状況でも、決してあってはならぬことなのだ。
一人一人のインカの民を守るために、やむなくこの反乱を起こしているのだ。
その反乱のために、民がかえって不幸な死を迎えるなど、決してあってはならぬことだ。
たとえ、一人の命でも、その重さは我々と変わらぬものなのだ。
わかっておくれ」
しかし、アパサは、既にトゥパク・アマルを見ようともしない。
「おまえが殺(や)らぬのなら、俺が殺る。
既に兵をすぐ近くまで連れてきているのでね」
憎々しげにそう言うと、「あばよ。もう会うこともないだろう」と踵を返した。
「アパサ殿、待たれよ!!」
トゥパク・アマルの声が、にわかに鋭くなる。
「わたしに、もう少しだけチャンスをくれ。
それで駄目であれば、そなたの好きにするがよい。
だから、今暫く待たれよ」
だが、アパサは見向きもせず、天幕を出て行きかける。
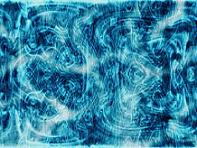
その瞬間、トゥパク・アマルが鋭い手つきで、天幕の出口で警護に当たるビルカパサに何かの合図を送った。
その合図を受けて、ビルカパサは一瞬、目を疑ったが、しかし、迷う間も無く、すぐにその命に従った。
ビルカパサは己の剣を抜き、天幕の出口に立ちふさがった。
さすがのアパサも、にわかに目を見張る。
「アパサ殿、ここをお通しすることはできませぬ」
低い声で言うビルカパサを鋭い目で睨んだ後、アパサはトゥパク・アマルを険しい表情で振り向いた。
「何の真似だ?!」
一方、トゥパク・アマルはすっと立ち上がって、アパサの方にゆっくりと歩みくる。
真正面からアパサを見据えるトゥパク・アマルのその表情には、今、一縷の感情も見えない。
アパサは、思わず固唾を呑んだ。
彼の傍まで来ると、長身のトゥパク・アマルはアパサを見下ろすようにして目を細めた。
「アパサ殿、今、そなたが褐色兵を討ちに行くと言うのであれば、ここをお通しするわけにはいかぬ。
暫く、この本営をお出にならぬよう、そなたには見張りをつける。
アパサ殿、これはただの脅しではない。
わたしは、本気だ」
背筋も凍るような無機質で抑揚の無い声である。
「トゥパク・アマル…!
おまえ…まさか俺を監禁するつもりか…?!」
アパサは予期せぬ展開に驚きと、そして、突き上げる激しい憤怒と苛立ちを感じつつも、一方で、どこか身の毛のよだつのを感じた。
トゥパク・アマルの感情の無い、能面のごとくの、その表情を再び見る。
その全身からは、青白い光のようなものがジワジワと放たれはじめている。
(こいつ…――!!)
アパサの額に、いつしか油汗が滲みはじめた。
その顔面が、にわかに引きつる。
その時、アパサは、トゥパク・アマルのもつ、ある種不気味な空恐ろしさを、はじめて体感していた。
そして、同時に、アパサにとっては単なるトゥパク・アマルの廉潔のなせる失態と思っていたクスコの敗退劇が、その裏に、激烈なほどにゆるぎなき彼の信念と決意があってのことであることを、この局面に至ってはじめて認識させられてもいた。
アパサの引きつっていた口元に、微かに苦笑が浮かぶ。
「ふん…。
褐色兵の将と話し合うだと?
おまえ、本気でそんなことが通じる相手だと思っているのか?」
「アパサ殿、わたしに任せてくれ。
何事もやってみなければ、わからぬ。
それに、わたしには、説得できる自信もあるのだ」
「チッ!!
おまえ、いつもそう言っておきながら、此度のクスコ戦でも惨敗しやがったくせに!!」
アパサの暴言ぶりに、トゥパク・アマルの脇に控えるディエゴが、激昂の表情で再び一歩を踏み出しかけるのを、トゥパク・アマルが無言のままに鋭い手つきでそれを制した。
トゥパク・アマルは沈着な、低い声で続ける。
「アパサ殿、何事もやってみなければ、わからぬ。
民の犠牲を最も少なくするための方略を、我らは追及し続けなければならぬのだ。
それは、戦乱の今の時期にあってこそ、忘れてはならぬことだと、わたしは思っている」
憎々しげに己を睨みつけているアパサを見つめるトゥパク・アマルの目には、蒼白い焔が燃え上がる。
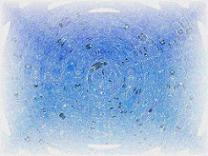
アパサは、その目の色を確かめるように、喰い入るほどにトゥパク・アマルの顔面を見据えてから、再び、「チッ!!」と舌を鳴らした。
「トゥパク・アマル…おまえは、いつだってそうだ!!
結局、おまえは、俺の話など聞く耳なんか、もたねえんだっ!」
「アパサ殿!
そのようなつもりでは…!」
「ああ、ああ、もういいって!!
おまえの好きにしやがれってんだ!
はいはい、わかりましたって。
今は、褐色兵に手は出しません、はい、トゥパク・アマル様!…ッテんだ。
クソッ!!」
アパサの完全に不貞腐れた皮相な態度に、トゥパク・アマルを囲むようにしている他の側近たちの顔色は、憤りやら、呆れ返りやらで、すっかり赤くなったり、青くなったりしている。
だが、トゥパク・アマルの表情は動かない。
「アパサ殿…」
「だからっ!!
おまえの、好きにしろって言ってんだろうが!!」
「アパサ殿、本当に、わたしに任せてくれるのだね?」
トゥパク・アマルは、相も変わらず、あの感情の無い能面のごとくの表情で、真意を探るように、じっとアパサを見下ろしている。
アパサは、そのトゥパク・アマルの視線を鬱陶しそうに手で払いのける仕草をした。
「おまえっ!!
俺の話が聞こえねえのか?!
リマの褐色兵はお前に任せるって言ってんだよ、俺は!!
ああ、そうとも。
今暫くは…、な」
「本当だね?」
トゥパク・アマルがやや目の色を和らげ、念を押す。
「ああ、だから、その化けて出そうな顔はやめろ!!
監禁もごめんだ!!」
やっとトゥパク・アマルは頷き、手でビルカパサに合図を送る。
同盟者として、そして、アンドレスの師として、もう長い付き合いになる眼前のアパサは、どのような形であれ、一度決めた約束を違(たが)える男ではないことを、トゥパク・アマルは既によく知っていた。
トゥパク・アマルの合図を受けて、ビルカパサは瞬時に剣を収めて後方に退(ひ)いた。
アパサも、ふっと小さく息をつく。
彼は、まだ納得しきれている表情ではなかった。
だが、それでも、一応の決が出た今、いつまでも云々といい続けても不毛であることも知っていたし、実際、このトゥパク・アマルがそこまで言うなら、一旦、任せてみる価値もあるか、とも、思えてこぬでもなかった。
そして、まず何よりも、今は互いに力を合わせ、いかにこの危機的局面を打開していくかの方がよほど重要であると、本質的には賢明なアパサには、そのことも良くわかっている。
結局は、トゥパク・アマルがアパサに今も篤い信頼を置いているように、アパサも、表面では何と言おうとも、彼もまた、内心ではトゥパク・アマルを変わらず深く信頼してもいたのだった。
二人は、改めて互いの顔を見据え合い、無言のままに、今、やっと、その眼差しで深く頷き合う。
それから、先刻までの、あの不貞腐れた調子とは異なる真面目な声で、アパサが言う。
「トゥパク・アマル、気をつけろよ。
おまえの首には、2万ペソ(註:邦貨に換算して約1千万円)もの大金が報奨金として懸けられている。
たとえ、同族同士でも、決して甘くは見るな。
おまえのように、いかにも清廉潔白な上に、金(かね)の本当の苦労など知らぬ奴には、金の本当の魔力はわかるまい。
あれだけの大金が懸かっていれば、…あるいは、今は敵でなくとも…目の眩む奴が出てこないとも限らぬ。
おまえには、生きててもらわにゃならんのだ。
この植民地体制を突き崩すまでは、な」
トゥパク・アマルも、いつもの穏やかな眼差しに戻って、深く頷き、微笑んだ。
「そなたの言葉、深く肝に銘じよう。
ありがとう、アパサ殿」


